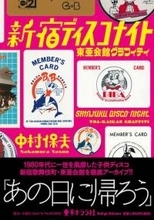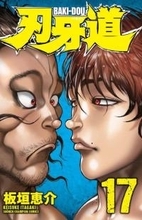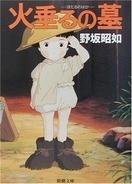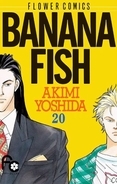バーガーキングが日本再上陸を果たした2007年には復活1号店にファンが長蛇の列を作るさまが報道されたし、ウェンディーズが日本から撤退した2009年には、別れを惜しむファンが大勢店舗に押しかけたことが伝えられた(今年後半に再上陸するそうなので、そのときにはまたニュースで取り上げられることだろう)。やはりファストフードの中でもハンバーガーは別格だ。新メニューが追加されるという報道がされただけでファンが大騒ぎするようなジャンルというのは、他にないだろう。
そのハンバーガーの歴史について詳細に調べた本が訳出されたので、読んでみた。邦題はそのものズバリ、『ハンバーガーの歴史 世界中でなぜここまで愛されたのか?』である。
2006年11月、テキサス州の議会に、同州のアセンズを「ハンバーガー発祥の地」とする議案が提出され、翌年可決された。もちろんこの決定が全米で認められたわけではなく、ウィスコンシン州シーモア、ニューヨーク州エリー郡、コネティカット州ニューヘブンなど、「発祥の地」として名前の挙げられる都市は他にいくつもある。
サンドイッチは、18世紀末で誕生した。生まれ故郷の国ではどちらかといえば上流階級の食べ物だったが、大西洋を渡ったアメリカでは労働者のものとして定着した。そうしたサンドイッチの具として牛の生肉を薄く削いだものがよく使われたが、健康面の問題から生食に警鐘を鳴らす医師も出現して、火を通す食べ方が推奨されるようになった。1876年のフィラデルフィア万国博覧会で肉挽き器が紹介されて普及したこともあり、挽肉を食べるという食習慣は全米で急速に広まっていった。
一方、ドイツ系の移民が本土でよく食べていた、挽肉をこねてまとめ、焼いた料理をアメリカの料理店でも出すようになっていた。フィラデルフィア博覧会に出店したドイツ料理店でその「ハンバーグステーキ」(本来のハンブルグビーフは高級肉のことだったという)が好評を博し、それがきっかけで広く国民に知られるようになった。このハンバーグステーキをパンに挟んで食べるという方法を、19世紀末の誰かがどこかで編み出したのだ。
スミスはそれぞれの年代で発表されたレシピ本を傍証に引いている。たとえば1875年に刊行されたエリザベス・S・ミラーの著書には生肉を塩、こしょうで味付けした「ビーフサンドイッチ」が載っているだけだが、1927年のフローレンス・A・ニコルズの『Seven Hundred Sandwiches』にはすでに、焼いたハンバーグを挟んだサンドイッチが紹介されている(ただし、丸のままではなく細かく切ったもの)。
『ハンバーガーの歴史』の叙述の白眉は、ハンバーガーのフランチャイズチェーンの興亡史について触れた部分だろう。
最初に成功を収めたのは、1921年にJ・ウォルター・アンダースンとエドガー・ウォルドー・イングラムが共同で始めたホワイト・キャッスルだった。それまでのハンバーガーは移動式スタンドで売られるのが常だったが、ホワイト・キャッスルはシカゴ・ウォーター・タワーを模した、白い印象的な建物を店舗として使用した。白は清潔感の象徴であり、肉体労働者向けの不潔な食べ物というイメージを一掃する狙いがあったのだ。ホワイト・キャッスルは、店員に制服を着せたり、自社で肉の加工場を持ってどの店舗でも同じ商品を提供できるようにしたりするなど、現在のフランチャイズチェーンの原点ともいえる戦略を展開している。
ホワイト・キャッスルの成功は他の業者の参入も呼び、ハンバーガー業界全体が大きく成長した。だが、第二次世界大戦によってもたらされた変化が、業界にも深刻な影響を与えることになる。郊外の住宅地が発達し、都市の住民がそちらに流出して都心の人口が減るドーナツ化現象が起きた。その結果、二十四時間営業をしていた都会のハンバーガー店舗にホームレスがたむろするようになり、清潔で売っていたイメージが大きく損なわれることになったのだ。こうしてホワイト・キャッスルなどの既存チェーンは失速し、代って郊外に展開した新規勢力が台頭してくることになる。その代表格が、マクドナルドだ。マクドナルドは、店内ではなくそれぞれの車内でハンバーガーを食べるドライブイン・タイプの店舗で業界に乗り込んできた。第1号店ができたのは、ロサンゼルスから東に160キロメートルほどいった町サンバーナディノである。
創業者はモーリスとリチャードのマクドナルド兄弟だが、システムを確立してチェーンを拡大したのは、彼らから事業を買い取ったレイ・クロックだ。初期のマクドナルド店舗は同業者から注目され、多くの者がマクドナルド・システムに学んでそれぞれのフランチャイズ・システムを確立していった。その中にはバーガーキングのようなマクドナルドの競争相手もいるし、ケンタッキーフライドチキンのように隣接業界の者もいる。逆にマクドナルドが他の業界から学んだことも多い。ドライブイン方式の目新しさが薄れ、1967年にバーガーキングが店内に椅子を置くやり方を始めたときは、翌年にマクドナルドも追随している(1971年に日本の第1号店であるマクドナルド銀座店が開業したときは、歩きながらハンバーガーを食べる客の姿が話題になった。店舗内で食事をさせないスタイルは、本国でもまだ主流だったことがわかる)。また、1968年に全国で販売が開始されたビッグマックは、バーガーキングのワッパーに対抗して考案された商品だ。
本書には、世界各国におけるハンバーガー受容史も記されている。ハンバーガーの自国への侵入を文化的な侵略と見做し、排除を図ろうとした国は案外多い。ハンバーガー会社(主にマクドナルド)は、その国の文化になじむためにさまざまな試行錯誤をして、そうした反発を乗り切ってきたのである。たとえば牛肉食をタブーとする人が多いインドでは、画期的な商品が考案されたことでマクドナルドの浸透が一気に促進された。ヴェジタリアン向けの「マックアルーティッキ」がそれで、じゃがいもと豆でつくったパティやトマト、玉ねぎをはさんでスパイシーな味つけをしたハンバーガーである。テリヤキバーガーやライスバーガーといった和洋折衷食を発明して、積極的にハンバーガー文化を採り入れてきた日本のような国はむしろ少数派だということが、この章を読むとよく判る。
笑ってしまったのは、モスクワや中国における事例で、従業員が笑みを浮かべるというマクドナルドのマニュアル対応が、かえって客に疑念を抱かせたというのだ。飲食店のスタッフが笑顔を見せるという慣習が、これらの地域には存在しなかったからである(さすが共産圏!)。日本ではあまり抵抗なく受け入れられている「スマイル0円」のサービスも、ところによっては逆効果になるものなのだ。
こんな具合にハンバーガーの過去と現在を知ることができる(そして、ちょっぴり未来の展望も)。巻末にはさまざまなハンバーガーのレシピも掲載されており、お得でもある。版元のブルース・インターアクションズは〈ぼくらは何を食べてきたのかシリーズ〉として、今後も食物史に関する本を出していくそうだ。次回作は『チーズの歴史』。注目していきたい叢書である。
(杉江松恋)