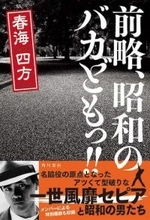――東日本震災があった3月11日、藤村さんは関西にいたそうですね。
藤村 大阪にいました。
――地震のことを知ったのはいつ頃だったんでしょう?
藤村 夕食後ですね。しつこく携帯電話が鳴るので仕方なくチェックすると、会社からの身元確認だった。その時点で連絡がつかなかったのが僕と数人くらい。慌ててテレビをつけると、想像を絶する光景が広がっていた。そのときの僕は、家族の前でつとめて平静に振舞うことで精一杯でした。
――地震後、“どうでしょう”公式サイト内のブログに藤村さんと嬉野さんが代わるがわる「各自の持ち場で奮闘しよう」という趣旨のメッセージを書いていたのが印象に残っています。
藤村 ちょうど翌週から宮城県や岩手で新シリーズの放映が始まるというタイミングでした。だから、北海道に戻ると、いつも通り編集室にこもり、新作の編集作業をしていました。こんな状況の中で放送してもらえるのか、見てもらえるのかはわからない。でも、もし放送してもらえるのであれば、楽しませる用意はあるぞ、と。
――ブログには「いろいろ落ち着いたら、来年あたり、また『祭り』をやりましょう」ともありました。
藤村 目標を持つことって大事だよなと思うんですよ。例えば、被災地にいる“どうでしょう”ファンにとっては「来週こそ“どうでしょう”を見たい」「また来週も見るぞ」という気持ちが支えになるかもしれない。テレビを見るためには倒れたテレビを元の場所に戻さなくてはいけない。場合によっては修理や買い替えが必要かもしれない。そもそも屋根がある場所にいて、テレビをのんびり見ていられる“日常”を取り戻す必要がありますから。
――震災以降、ものづくりの基準や考え方が大きく変わるのではないかという話をよく耳にします。
藤村 脚本の書き直しや、企画を根本から見直すといったようなことはどこの制作現場でも起きているでしょうね。ただ、ものづくりの基準がこれまでとまったく違うものに変わるわけではない。「この程度でいい」と“なあなあ”で済ませるという選択肢がなくなるだけですよ。
――藤村さん自身のものづくりに対するスタンスは変化しない……?
藤村 僕は超現実主義なので、変わりようがないんです。目の前にある課題をひとつひとつ片付け、1日、1時間という時間の流れの中で笑いを生み出していくのが“どうでしょう”のスタイルですから。面白い映像が撮れなければ、24時間カメラを回し続ける。
――ありましたね。「東北・生き地獄ツアー」シリーズの「腹を割って話そう」事件!
藤村 いきあたりばったりということでいうと“どうでしょう”史上、最もひどかったのは「激闘! 西表島」でしょう。僕は本気でカブトムシをとりにいくつもりだったんですよ。昼間はビーチで昼寝をし、夜になったら昆虫採集という計画だった。ところが、現地入りしたらコーディネーターのロビンソンが「虫はつまらない」とバッサリ。
――“どうでしょう”はゲストにも恵まれていますよね。みなさん驚くほどキャラが濃くて……。
藤村 あれは運がいいわけではないんですよ。ガイドさんはね、まず間違いなく面白い。お客さんを楽しませ、その土地の魅力を伝えるのが彼らの仕事ですから。まだ出くわしてはいないけれど、やたらとテンションが高いガイドがいても不思議じゃない。真っ黒に日焼けしたヤツに「イェーイ! 楽しいですかぁ!!」と叫ばれ、「おお……、楽しいよねぇ……」と、おっさん4人がゲンナリする。こういった具体的な絵が浮かぶものは、必ず面白くなります(笑)。
“答え”は常に現場にある。でも、“けものみち”を見出すにはそれ相応の眼力が必要。無数の経験に裏打ちされた藤村メソッドに触れることは、借り物の知識では到達できない未知なる領域への第一歩になる(島影真奈美)