企業向けアプリのUIはどう設計されているの?――日立デザイン本部に聞いてみた:「モックアップを何十個も作る」
アプリケーションの使い勝手には、機能と同等にそのインタフェースが影響する。実際のデザイン業務はどのように進められているのだろうか? デザイナーに聞いてみた。
「デザイン」という言葉に対して、どのようなイメージをお持ちだろうか。記者の場合は、雑誌編集を経験していることもあり、誌面やポスター、パンフレットなどのデザイン(いわゆるDTP)を連想する。もちろんインテリアや、あるいはファッションデザインを想起する人もいるだろう。
こういった分野では、プロダクトに占めるデザインの役割が明示的であり、分かりやすい。だが実際には、われわれが手にし、あるいは目に、耳にするプロダクトは(程度の差こそあれ)デザインされたものであり、そこに意匠を施した組織、人物が存在する。もちろん工業製品においても例外ではない。
国内最大の総合電機メーカーである日立製作所(以下、日立)の場合、グループ内のデザイン業務を一元的に担う「デザイン本部」を設けている。これは最近のことではなく、デザイン本部の発足は1957年。つまり今年で設立53年という歴史を重ねている組織だ。
発足当初は家電製品のデザインが主だったというが、日立 デザイン本部 経営戦略室の和田紀彦 主任デザイナーは「他社の同種の組織と異なるのは、デザイン領域が医療であったり、鉄道やエレベーターであったりするなど、家電以外の社会的インフラを担うものにまで拡大していることです」と話す。ひいてはユーザーインタフェースやソリューションそのもの、そして社会システムやイノベーションの方向性についても“デザイン”を試みているそうだ。「人間が直接触れられないものにまで、デザイン領域が拡大しています」(和田氏)
日立の、そしてデザイン本部のフィロソフィー(理念、コンセプト)をまとめると「エクスペリエンスデザインの創造(ユーザーの思考や行動を洞察し、ユーザーの好ましい経験価値を創出する。そして、その価値を分かりやすく伝え、共感を得る)」だという。要はユーザーに対し「思い通りに使える」とか「気が利いている」という“主観的な経験価値”を与えられるのがデザイナーの仕事であるという考え方だ。
「創設50周年を迎えた2007年頃から、経験価値の創出のため“対話”をデザインフローの軸に据えました。具体的には“深く知るための対話”“創造的な対話”“モノを通じた対話”そして“実践につなげる対話”の4つです」と和田氏は話す。従来は、1人のデザイナーが職人的にデザインを進めていた部分もあるというが、今ではこれらの対話プロセスをPDCAサイクルのように回すことで、下部工程だけでなく、より上流工程から、製品開発に参画できるようになっているという。
観察だけでなく、参加によって課題を洗い出す
プロセスの実際を、幾つか紹介しよう。例えば“深く知る”ためには、ユーザーの利用環境を徹底的に現場観察することが必要だ。デザインに着手する際には「利用状況調査」を実施しているといい、そのことをエスノグラフィー(Ethnography:文化人類学で発展した異文化理解のための研究手法)と呼んでいるという。
エスノグラフィーには、専門のスタッフが当たる。ユーザーから問題点を聞き出すだけではなく、ユーザーの無意識な行動を観察し、そこに潜む隠れたニーズを見つけ出す(例えば、医療機器をデザインするなら、実際に病院現場に赴き、医師や検査技師などの作業を細かく観察する)。これにより、普段はユーザーが無意識に、あるいは当たり前に実施している(非効率な)作業フローに対して、外部の人間として気付きを得られる。こういった気付きは、現場のユーザーにヒアリングするだけでは得られないものだ(ユーザーは自分が気付いていることしか回答できないから)。
また“モノを通じた対話”としては、早期にプロダクトを具体化することが挙げられる。例えば、デザインを依頼してきた顧客(日立グループの企業であることもあれば、そうでないこともある)との間でプロダクトのコンセプトを共有できた段階で、仮の製品カタログなどを制作してしまい、最終製品化イメージの叩き台とするのだ(もちろんこういった作業は、デザイナーが従来から得意としてきた分野だともいえる。このように具体化されたものを元にデザインフローを進めることで、顧客と円滑に合意形成したり、コンセプトのブレを防いだりできるという。
国分寺で発足し、その後、青山にもオフィスを拡大した同本部だが、上述のような対話プロセスを回すとなると、課題も表面化してくる。今ではデザイン本部の業務自体がハードウェアだけ、あるいはソフトウェアだけでは完結しないため、密なコミュニケーションが求められるが、オフィスが分散配置されていると、デザイナー同士はもとより顧客とのコミュニケーションも物理的に難しいからである。
そこで2008年に、現在の赤坂オフィスに統合。今では約150人の社員が勤務している。オフィスの構成は大まかに「ユーザビリティラボ」「インキュベーションスタジオ」「プレゼンテーションルーム」そして「モデリングスペース」と(対話プロセスに基づき)分類された。
「(オフィスの統合により)他のスタッフの仕事を普段から目にすること自体が刺激となりますし、一貫して何かをデザインする際には、より効率よくコラボレーションできるようになりました」と和田氏は話す。
2010年10月にリリースされた中堅中小企業向けの運用管理ソフト「Hitachi IT Operationsシリーズ(以下、ITO)」は、同本部がインタフェースの設計を担当し、米国のデザインアワード「IDEA(インターナショナルデザインエクセレンス)」や、日本のグッドデザイン賞(いわゆるGマーク)を受賞した。新しい環境ではどのようにデザイン業務が進められているのか、同ソフトウェアを例に、担当デザイナーの藤井 勉氏および伴 真秀氏(どちらも情報ソリューションデザイン部)に聞いた。
――ITOの開発にデザイン本部が携わったきっかけはどこにあったのですか。
藤井 今回の製品は、中堅中小企業をターゲットとしています。この市場はある意味、日立としては“新規参入”だとも言えます。分厚いマニュアルを読んだり、難しいトレーニングを受けたりせずとも、例えばiPhoneのように、とりあえず使えてしまうようなインタフェースでなければ、という考えがありました。
このことはユーザーだけでなく、ITOを再販するパートナーにとってもメリットがあります。製品を提供する側が細かく機能を説明しないと売れない、という状況ではなくて、ユーザーのほうから列をなして買う順番を待つ、といった状況が理想的だからです。ITOのような価格帯の製品の場合、ユーザーにとっての使いやすさだけでなく、売る側にとっての手離れも重要になります。
――デザインのプロセスについて教えてください。
藤井 ISOで「人間中心設計プロセス」というものが規定されており、こちらに従って(インタフェースの)デザインを詰めていきます。今回はまず、ITOユーザーのモデルとなる“ペルソナ”を設定し、(インタフェースの)設計と試作を進めました。同時にITOの想定ユーザーに試用してもらい、ユーザーの欲求を満たしているものになっているかどうかを検証しています。このように、フィードバックを受けつつ改善していくというプロセスを何度も回しながら、練り上げました。期間としては、3カ月ほどでしょうか。
一般に業界では、上流工程で決定した仕様は、下部工程にいたるまで徹底的に順守し、開発される傾向があります。ですが今回は、ユーザー模擬利用やモックアップなどの検証段階などで課題を指摘された場合、改善方法をデザイン側と開発側でディスカッションし、柔軟に対応しました。大規模なソフトウェア開発の世界で一般的とされる手法を変えてしまったわけですね。
もちろん毎回、デザイン側と開発側の見解が一致するわけではありません。ですが“対話プロセス”を実践し、ディスカッションを続けることを、強く意識して進めました。ディスカッションに際しては、開発側にも「インキュベーションスタジオ」に来てもらい、顔を合わせて会話することを心がけています。その際、言葉や文章だけではデザインの共有に限界があるので、なるべく事前に、モックアップを用意するようにしました。
ここで言うモックアップとは、単に画面をデザインしただけのものではありません。実際に発生する操作フロー(ユースケース)の範囲で動作する物を、FLASHで制作しています。数で言えば、数十件は作りました。開発側も、ソフトウェアとして動作するモックアップを複数作ってくれましたので、デザイン側としても助かっています。
――開発に際して気を使った点はありますか。
伴 ITOがターゲットとしている中堅中小企業には、専任の情報システム管理者が存在しているとは限りません。つまりITOを操作するユーザーは、日常は他の業務についているわけです。ずっとITOを眺めていられるわけではありませんから、障害が発生した際には、画面のどこを見て、どのように対処すべきかを、ユーザー自身が解析せずともすぐに分かるようにしています。また障害中は、ユーザー自身があせっていることも考えられますから、その心理状況も織り込みながらデザインを進めました。
デザイナー自身も、情報システム管理のプロフェッショナルではありません。だからこそ、ITOの想定ユーザーの目線でデザインできたと考えています。
――ITOのログイン画面は、従来からある日立のシステム管理製品とは一線を画すデザイン性だと感じます。
伴 ログイン画面にはこだわりました。例えば鏡面反射効果は実際の機能には関係ないですよね。でも、使っていて感じる心地良さや格好良さは、決してコンシューマー向け製品だけに求められるのではありません。企業で使うソフトウェアであっても、使うのは同じ人間ですから。
藤井 ITOは試用版をダウンロードした上で、購入できます。つまりわれわれとしては、試用版をインストールする段階でつまずいて欲しくはないわけです。ログイン画面の段階からデザイン性に配慮し、またインストールや初期設定画面の印象を“柔らかな”ものとすることで、ユーザーの心理的なハードルを下げようと試みています。決して、文字で解説すればよいというものではありません
伴 例えばメニューの表示と非表示を切り替える際に、普通に描画したり消したりするだけでも、機能要件は満たしています。ですが、表示/非表示の動作に感触を与えること(伴氏はそのことを、メニューが“しゅるっ”と出たり消えたりする、と表現)が、ユーザーの心地よさにつながります。こういった部分について、言葉で開発側と合意を得るのは難しいので、FLASHで最終形に近いモックアップを作り、納得してもらっています。デザインに当たっては、デザイナーの思いだけでなく、それを説明して理解を得ることが重要ですから。
――デザイン側と開発側との間で、意見のぶつかり合いはありましたか。
藤井 上述のとおり、すべての意見が一致するわけではありませんから、そういうこともあります。ですがITOについては、ユーザビリティへの意識が高い開発メンバーが多かったことと、モックアップを介した説明を心がけたことで、合意を得ていきました。最終的にはデザイナーが詰め切れなかったアイデアを、開発側から提案、指摘されることもありました(笑)。
伴 開発側からインタフェースについて意見をもらえると、コラボレーションしている実感があります。デザイナーとしてはとてもうれしいことですね。
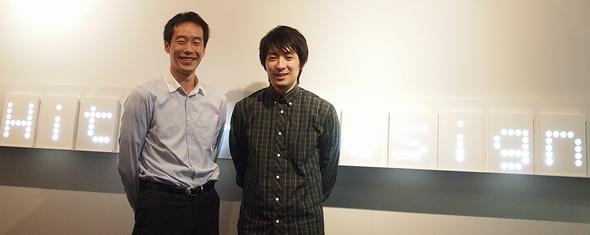 左から日立 デザイン本部の藤井氏と伴氏。それぞれ「他の人が無意識に使っているものが気になります。例えば外で食事をしていても、食器の材質や形状が気になってしようがない」(藤井氏)、「普通に美術館や博物館は好きですね。それとマンウォッチング。あと、自然界に潜む美しさに引かれます。実は動物の骨が好きなんです(笑)」(伴氏)とのこと。どちらもデザイナーになるべくしてなったと言うべきか
左から日立 デザイン本部の藤井氏と伴氏。それぞれ「他の人が無意識に使っているものが気になります。例えば外で食事をしていても、食器の材質や形状が気になってしようがない」(藤井氏)、「普通に美術館や博物館は好きですね。それとマンウォッチング。あと、自然界に潜む美しさに引かれます。実は動物の骨が好きなんです(笑)」(伴氏)とのこと。どちらもデザイナーになるべくしてなったと言うべきか関連記事
 日立、中堅中小向け運用管理ソフト「Hitachi IT Operationsシリーズ」を発表
日立、中堅中小向け運用管理ソフト「Hitachi IT Operationsシリーズ」を発表
日立は中堅中小企業向け運用管理ソフト「Hitachi IT Operationsシリーズ」を投入する。専任の情報システム部門を持たない企業をターゲットに、導入のしやすさ、使いやすさを追求した。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事ランキング
- 爆売れだった「ノートPC」が早くも旧世代の現実
- HOYAに1000万ドル要求か サイバー犯罪グループの関与を仏メディアが報道
- GoogleやMetaは“やる気なし”? サポート詐欺から自力で身を守る方法
- PAN-OSにCVSS v4.0「10.0」の脆弱性 特定の条件で悪用が可能に
- PHPやRust、Node.jsなどで引数処理の脆弱性を確認 急ぎ対応を
- Appleの生成AI「MM1」は何ができるの? 他のLLMを凌駕する性能とは
- OTセキュリティ関連法改正で何が変わる? 改正のポイントと企業が今やるべきこと
- Google、ゼロデイ攻撃を分析した最新レポートを公開 97件の攻撃から見えたこと
- 約半数の企業は“初期段階” アイデンティティーセキュリティに関する調査が公開
- 生成AIは便利だが“リスクだらけ”? 上手に使いこなすために必要なこと
 日立 デザイン本部、赤坂オフィスの様子
日立 デザイン本部、赤坂オフィスの様子 ログイン画面の鏡面反射効果。実際に打ち込んだ文字列も反射して見えるというこだわりよう
ログイン画面の鏡面反射効果。実際に打ち込んだ文字列も反射して見えるというこだわりよう ユーザー調査のもよう。ガラスの向こうで実際に操作してもらい、その操作方法や心理状態を各エキスパートが別室で評価する(イメージ画像)
ユーザー調査のもよう。ガラスの向こうで実際に操作してもらい、その操作方法や心理状態を各エキスパートが別室で評価する(イメージ画像) モックを元に検討している様子
モックを元に検討している様子 多くのパターンを作成する
多くのパターンを作成する ウィザードの段階でホスピタリティの高さを印象付ける
ウィザードの段階でホスピタリティの高さを印象付ける


