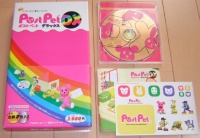1997年に登場した、パソコンの中のペットたちがメールを運ぶメールソフト「PostPet(ポストペット)」。1体しかいないペットがメールを届けに行くと、帰ってくるまで次のメールが出せない(その場合は「ポストマン」というロボットが対応してくれる)。届けた先の相手になでてもらったり、おやつをもらったり、その思い出を帰宅したペットは「ひみつ日記」に書いたりする。こんな、ある意味時代に先駆けすぎたコンセプトにもかかわらず、累計約1500万ユーザーを獲得し、パソコンへのバンドルや専用端末まで登場する人気作となった。メッセージのやりとりが、メールからSNS、ツイッターなどに移行する中、20周年を記念して、VR版の開発が進んでいるという。
しかし、現状でVR版を作っても、ユーザーはいるのだろうか? 手がけるのは「中二(中学二年生)のまま生きる技術」集団を公言するペットワークス。創業者の八谷和彦さんに、ポストペットVRを初めとする数々の新規事業の始め方、続けた方についてお聞きした。
ペットワークスはなんといってもジェット機まで作ってしまう会社(「OpenSky(オープンスカイ)」プロジェクトとして、1人乗り超軽量ジェット機「M-02J」を開発、昨年、場内周回飛行に成功。詳しくは「ナウシカの“メーヴェ”を本当に作って、飛んだ人に聞く」)ですから、VRくらいで驚いてはいけないんですが(笑)。いまVRでポストペットって、どういうことなんでしょうか。そもそもVR環境を持っているユーザーは、そんなにいないでしょう?
八谷和彦さん(以下八谷):今年は、「ポストペット」のβ版が世に出て20周年なんですね。1997年の年始にテストユーザー用のβ版が出て、その年末にパッケージ版の「ポストペット DX(デラックス)」が発売になりました。
今、こちらの会社(ナディア)に間借りしてVR版を作っているのですが、状況が20年前とそっくりなんですよ。当時はお茶の水にあったアイ・エム・ジェイに作業スペースを間借りして作っていました。居候して作っている感じがそっくり。だからといって、惨めな感じもないし、「やるしかない」みたいな切羽詰まった感じも、「一発当てようぜ」みたいな、デッドオアアライブな雰囲気もない。
とはいえ、会社ですから、必死だろうがゆるくやろうが失敗すれば赤字になって、続けていけないわけで。
八谷:もちろんです。だからこそ、VRコンテンツを作ることからリブート(再起動)しようとしているわけです。うちの会社はポストペットの開発チームを中心に創業してから19年、とても小さな会社ですが、「みんなが欲しいと思っているけど、まだ世の中にないもの」を作ることをモットーに、「航空事業部」「ドール事業部」「ソフトウェア事業部」とか好きなことをやってきて、幸いにも倒れずに済んでいます。
なにせ「中二のまま生きる技術」という題で展覧会開いたりしてますよね…。でも、「会社で好きなことをやる」のは、一度限りならできなくもないと思いますが、続けるのはとても難しいんじゃないかと。
仕事のコアは「プロジェクトマネジメント」
八谷:それはおっしゃるとおりですね。続いているのは運が良かった、というのもあります。お人形がちゃんとビジネスになるかとか全く考えてませんでしたし。「幸いにも、まだ死なずにいますなあ」というのが、正直な話かもしれません。
ナウシカの「メーヴェ」を本当にジェット機として作ってしまうM-02Jなんて、操縦者は八谷さん自身ですから、本当に死なずに済んで良かった。

八谷:物理的に死ぬ可能性があったのはあれくらいですが(笑)、一見、無茶なことをしているようで、とにかく、無理なことをしないように、それによる事故がないように、実はひとつひとつ積み重ねているんですよ。
自分が死ぬのも、会社が赤字で倒産するのもいやなので。リスクはなるべく最小限に抑えて、面白さを最大限にして生きていきたい。対象は飛行機だったりソフトウェアだったりしますけど、自分としてはやっていることは同じで、プロジェクトマネジメントです。自分の仕事のコアはそこだと思っているんです。
それは、「オープンスカイ」に参加した方の日記(こちら)を読んで改めて思いました。八谷さんの、プロジェクトマネージャーとしての信条みたいなものはありますか。
八谷:「自分から率先して面白がってやること」と、「それを通して周りの人に面白がってもらうこと」でしょうか。売上高とか利益の数字ではなく、何か具体的な目標を立てて行動していると、手伝ってくれる人が現れる。面白がってやっていると、「面白そう」という人が集まってきて手伝ってくれる。オープンスカイは「実機のメーヴェが飛ぶところをこの目で見たい」という方たちに、ものすごく助けていただきました。
実は最近、コンサルタントの方から「新規事業の作り方を教えて欲しい」という問い合わせがすごく多い、と聞いたんです。
八谷:そうなんですか?
資金はあるけれど、この20年、社内で新規事業を手掛けた人間がいない。なにをどうやって始めたらいいのか、全く分からない、と。
八谷:なんてうらやましい(笑)。
ということで、そうした需要に応えて、今回のポストペットの再起動プロジェクト、ポストペットVRが、どういうきっかけで始まり、何を目指すのか、プロマネの視点から教えてくださいますか。
八谷:きっかけは、2014年に、作品として「カイクイライド」というVRシミュレーターを開発したことです。
カイクイライド…ああ、「風の谷のナウシカ」のトリウマ(名前が「カイ」と「クイ」)に乗れるやつですね。
八谷:メーヴェをモデルにしたM-02Jの開発中にも、フライトシミュレーターを作ったのですが、こちらの体重制限が60kgなので大人の男性のほとんどが乗れない。
最初はやっぱりナウシカだった?!
八谷:そこで、多くの男性のためにも体重100kgの人が乗れるコンテンツを、と思ったんですけど「ただし、貴方はナウシカではなく、ユパさま担当で」と、カイクイライドになりました。
こちらは、「Hashilus(ハシラス)」という、乗馬スタイルの家庭用トレーニングマシン「ジョーバ」とVRを組み合わせたシミュレーターがありまして、当時それを開発していたチームと一緒につくりました。現在ハシラスはJRAのイベントや、ハウステンボスでの常設展示で大人気なんですが、このハシラスを改造して、乗馬レースではなく「トリウマに乗って、巨大な王蟲に追っかけられる」という作品に仕立てたわけです。この時点では試作品として作っていて「俺も王蟲に追っかけられてみたい」みたいな動機で全員がボランティア、な感じの開発だったんですが、それを作ってみて「VRコンテンツって架空世界に入り込めて本当に面白い」と気づいたんです。

それでも、最初はポストペットと合わせる考えはなかったんですけど、UEI 社長の清水さんが主催した、「VRヘッドセットのHTC Vive(以下Vive )を買ったので自慢する会」というのにおじゃましまして、Viveで初めてハンドコントローラーを使えるデモを見せてもらって、「これはさらにすごい」と感じて。
例えばVR空間の中にロボット犬がいて、こちらが枝をつかんで投げると取ってきてくれる。それが単純なのにすごく楽しかったんです。もうひとつ感心したのは「ジョブシミュレーター」。オフィスワークからファストフードの店員まで、たくさんのお仕事をバーチャル体験するソフトですね。これが、(データ量が小さい)ローポリゴンで描写されていて、決してリアルではないんだけど「VRって、もしかして、ローポリゴンの方がいいんじゃないか」と気づいた(ジョブシミュレーターのデモ画像はこちら)。
「触れる」ことと「ローポリゴン」を切り口に、VRをポストペットと合わせるとすごく面白くなるのではと思って、ぜひやりたいなと。
しかも20周年だし、と。
まずは、13年前の3Dデータを流用
八谷:ポストペットで組んだプロバイダーのソネット(編注:現社名はソニーネットワークコミュニケーションズ)の方と、「20周年、どうしましょうか」という話を昨年からしていたので、「ペットワークス企画でVR版ポストペットを開発したい」と提案しました。しかし、今はVRのコンテンツを作ってもユーザーがすごく限られるので、ソフトの販売単体でペイできるとは考えていません。
そうですよね。VR環境をパソコンで備えるとなると、いわゆるゴーグルだけで10万はかかります。パソコンもハイエンドクラスで15万くらいはするでしょう。
八谷:…という冷静さもありつつ、一方で自分たちが昔作って、多くのユーザーの方に愛されたポストペットの世界に入ったらどうなるか、これはやってみたい、と。リクープ(投資額の回収)ができなくても、これはやる価値があるし、過去のユーザーの方にぜひ体験してもらいたいと思ったんです。試しに2002年に出た、「ポストペットV3」の3Dデータをベースに試作してみたら、想像以上に面白いんですよ。論より証拠、ちょっとやってみませんか。
! ありがとうございます。
ようこそ、ローポリゴンの世界へ!
うわ…VRってこういうふうに見えるのか。お、モモ(ポストペットのメインキャラクター)がいる。撫でていいんですか…まさかお前にこうして会えるとはなあ。だっこは…あ、さすがに出来ないんですね。

八谷:これをやった方は十中八九、モモをだっこしようとしますね。なるべく早くだっこは実装したいと思ってます。
膝の上くらいで、抱き上げたくなる高さなんでしょうね。
八谷:お子さんがいる方なら実感としてわかるでしょうけれど、子供の小さい頃の身長に設定してあります。4歳児くらいかな。自分の子を抱き上げた思い出があると、街中でもそこくらいの身長の子がいるとつい「だっこさせてくれませんか」…とは理性が止めて言わないけれど(笑)、本能的にはあるじゃないですか。
おっさんが口に出したら社会的にNGですが、きゅんと来ますね。
八谷:だっこしたり、手からおやつをあげられる、とかも、機能として装備したいですね。
あ、モモの部屋の家具や冷蔵庫ってこんなに小さいんだ。
八谷:これはVRで作ってみて初めて実感として分かりました。「宝箱ちっちぇー! お、開けたいぞこの冷蔵庫!」と。中からはドット絵のおやつがでてくる。むしろドットがいいわ、と。
現実の世界にペットたちが3Dになって出てくる、というのじゃなくて、キャラクターの世界に入り込んだ気分になりますね。
八谷:そう、やってみるまで面白いかどうか分からなかったんですけど、やってみたら「ローポリでも、いや、ローポリだからこそ、自分が世界に入った時の相性がいいな」と。
現状ではVRソフトは、映画俳優みたいなルックスの3Dの人間が動くのも出ていますけど、ポストペットV3のポリゴンは2002年のPCで動かすのが前提の、小さなデータ量なんですね。だからリアルさはない。でも、別の世界に入ったときに、出てくるのが「よくできた人間」だと、かえって「らしくない」部分を探してしまって、「CGだ」としらけたりします。
こっちのほうは最初からローポリゴンのキャラクターですから、違和感がない。欧米は、現実と同じリアル世界にどうやってユーザーを連れて行くか、で作っているけれど、ジョブシミュレーターやポストペットVRは、「自分がローポリの世界に行く」考え方なんです。
VRはゲームの魅力を蘇らせる
そうなると、VR化で昔の作品に別の魅力が見えてきたりしませんか。
八谷:まさにそうです。ゲームで「セガラリー」や「スペースチャンネル5」などを手がけ、セガから独立された水口哲也さんが作った「Rez」(2001年発売)という、シューティングと音楽を合体させた名作がありますが、これが昨年10月に「Rez infinite」として、プレイステーションVR(以下PSVR)用にリメイクされました。シナスタジア(共感覚)スーツという特製スーツを着て体験させてもらったんですが、これがすばらしくて。
シューティングと音楽の一体化というコンセプトは同じでも、平面のディスプレイを眺めるのではなくVRで「その世界に身体ごと入る体験」となると、音と自分のアクションがダイレクトにつながって、全然別物といっていいくらいです。Rezも初代は2001年くらいのゲームなのですが、それがVRでリメイクされることで、本質的なところが強調されるのでしょうね。コンテンツによっては、数十年前のソフトが蘇ることもありえると思います。
話をポストペットVRに戻して、もうひとつ面白いのは、やっている人を外から見ると、これが案外愉快なんですよ。
そうですか? じゃあ、カメラマンのOさん、ちょっとこれ付けてみてくれません?
カメラマンOさん:ええ? 僕がですか?

Oさん:おー、かわいいかわいい(けっこう夢中でモモを撫でている)
なるほど、これはなんというか、外から見ると実におまぬけになってしまって、いいですね。
八谷:いいでしょう? 任天堂の「バーチャルボーイ」がそこまで流行らなかったのは、1人でVRゲームをする、という点にあったと思うのですが、最近のVRブームは、アトラクションとして皆で楽しむ、という方向に行ったのも大きいんじゃないかと思うんです。
そういえば「カイクイライド」の時も、「ゴーグル付けて、ジョーバに乗って、扇風機の風を受けながらぎゃーぎゃー騒いでいる大人の男性」を見ているのは結構面白かったです。
スマホで育てて、モールで会おう
八谷:先ほどおっしゃっられたとおり、現状ではVRを体験するには一般ユーザーにとってはかなり敷居が高いんですが、逆に、企業が投資したリッチな体験設備が集客装置になるのではと考えています。たとえば、バンダイナムコさんが東京・お台場、現在は愛知県・長久手のイオンモールに「VR ZONE」というVR体験施設を作っていますが、インタビューによると、VR体験を予約して、待ち時間の間に買い回りしてくれる、昔の百貨店の屋上遊園地みたいな効果が期待できるとのことです。VRは、ショッピングモールにいる滞在時間を長くしたり、来店機会を増やすことに貢献する、と。
そこのソフトとしては、ホラーとか、シューティングとか、エクストリーム系スポーツとか、どきどきハラハラさせるコンテンツが多いんですけど、中に「かわいいコンテンツ」があってもいいんじゃないか。自分が育てたキャラと遊べるものに発展できるかもしれない。
あ、普段使っている自宅の環境では2次元でしか会えないけれど…
八谷:スマホで育てて、モールに出向けば立体になって一緒に遊んでくれる、なんて、面白くないですか。
おお。なるほど。
八谷:そういうことも先々考えています。そのためには、自分たちが作ってみて、どうやったら楽しくなるのか、ノウハウを溜める必要があるわけです。ポストペットVRの売上で稼ごうとは思っていなくて、むしろユーザーへの感謝として作るんですけど、研究開発ではあって、これの先になにか金脈ありそう、今できるなら積極的にやってみよう、と思って。
開発費を、「キャンプファイア」でのクラウドファンディング(こちら)で募っていますね。
八谷:はい。コスト面の話をすれば、昔のゲーム機、例えば初代プレステ、64とかの時代は開発する際に、プラットフォーム側が提供するライブラリ(ソフトを作るためのひとまとまりのプログラム)を使っていて、開発にはかなりの費用がかかりましたけれど、いまは汎用のゲームエンジンやライブラリが、無料だったり非常に安い値段で手に入ります。ハードも安価になって、開発は凄くやりやすくなっています。ポストペットVRはUnityで開発しているのですが、大学の教員、メディアアーティストとして学生さんにアドバイスするためにも、VRは手を付けておきたいジャンルだ、というのもあり。
蒲田温泉で、モモと握手
八谷:とはいえ、クラウドファンディングで全額をまかなおうとは思っていなくて、共犯者…というと言い過ぎですね。ユーザーさんと一緒に作る、マーケティングの一環とする、という目的の方が大きいです。目標額が集まらなくても、自分たちがやりたいことをコアなユーザーさんにちゃんと伝えられますし。オープンスカイもそうでしたけれど、大事なのは、ちょっとずつ、プロセスごとに、実現に近づき中身が変わっていく様子を、関わってくださる方々に見せて、面白がっていただくことです。

初代のポストペットがまさにそうでした。β版を公開し、ユーザーの皆さんに助けてもらいながら、プロバイダー毎のクセを確認して安定性を高めていきました。あれと似た形にしたい、と考えてやっているわけです。
クラウドファンディングに参加してくださった方には、パトロンになっていただくわけですから、なるべく面白がってもらおうと思っています。シン・ゴジラ的に、東京上陸は蒲田から、と思っていまして、蒲田温泉(東京都大田区)の二階に宴会場があるので、3月のα2版の体験会は、そこで温泉付きの体験会にしようと思っています。今回、庭に温泉もつきましたし。
最近、「makuake」のクラウドファンディングを使った映画「この世界の片隅に」のプロデューサーの方から(記事はこちら)、「“いま何をやっているか、どこまで来たか”を、参加してくれた方々に報告するかをすごく意識した」と聞きました。
八谷:それはものすごく共感します。ちなみに僕もあの映画3回見ました(笑)。我々のもそうですが、「雪だるま方式」のプロジェクトってありえると思うんです。小さいこと、できることから始めて、具体的な成果や行動を通して周りを巻き込んでいく。収益モデルを立てて「このくらい資本が必要」と集めてからスタートするのではなく、でも無理はしないで、自分たちで出来る範囲でぼちぼちやってみましょう、という。
我々ペットワークスは全員で8人、常勤5人の小さな会社です。僕も芸大と掛け持ちですし。ちっちゃい会社って、変わり身の早さというか、恐竜時代の小さなほ乳類みたいに、適応力で生き抜くしかない。やりたいことがあるなら、すぐに手を付けておく。ビジネスになるかは、走りながら考える。オープンスカイはある程度赤字が前提でしたけれど、ポストペットVRは最終的にはちゃんとビジネスになるように考えていくつもりです。
今回は収益を考える。それはなぜですか?
八谷:大きな理由は、ポストペットを愛してくださる方々への責任ですね。オープンスカイのM-02Jは量産を前提としない試作機でしたけれど、ポストペットは多くのユーザーの“思い出”や“体験”を預かるわけなので、運用を始めて、サーバーを維持していく費用を考えると、我々の規模の会社では簡単には手を出せない。途中で簡単に「すみません、もう続けられません」と放り出すことはできませんから。
なるほど。
キャラクターのプラットフォームにもなれる
八谷:話が前後してしまいました。ポストペットVRは基本は「20周年盛り上げアプリ」なんですけど、その先にスマホ用のポストペットも当然考えていて、でもそれはメールソフトではありません。メッセージアプリとして作るつもりです。
ポストペットだけど、メーラーじゃないんですか。
八谷:僕らがメーラーとしての「ポストペット」の開発を止めてしまったのも、メールがスパムで汚染されて、スパムフィルターの性能がメーラーの品質を決めるようになり、最終的にはGメールなどが主流になったことがあります。その後、端末がすっかりスマホに移行したので、今やプライベートなメッセージのやりとりは、メールではなくFaceBookやLINEなどのメッセンジャー系になりました。
ですので、ポストペットVRでベースの開発をした上で、ゆくゆくはメッセージ機能をもつスマホ版を作りたいけれど、メッセンジャーアプリはダウンロード数が多くないと意味がないし、では、100万ユーザー、ということになると、今度はその環境を作って維持するのが大変です。
そこで、ポストペット20周年というタイミングで、まずペットたちと同じ空間で遊ぶことを目的としたVRアプリをPC先行で作ってみよう、と。これならユーザー数が限られますし、開発手段もそれほど費用がかからないから、リスクが少ない。そこでうまくいったら、スマホ版の試作作ってVR版と連携したい。
スマホ版は、例えばどんなイメージですか。
八谷:もちろん、スマホ版同士でペットにメッセージを託して運んでもらえるわけですが、それだけではなく、例えば、Yさんのスマホの中に、VRユーザー、例えばゴーグルをかぶった自分(画面内では紙袋を被ったキャラクター「アンノウン」になる)がペットのかわりに、メッセージ配達にやってきて、Yさんがスマホ上で僕のキャラを撫でると、自分の視点では、上から巨大な手でなでられていて怖い、みたいな。そこまでやれたら面白いですよね。

スマホとVRのリアルタイム連動って僕が知っている限りはまだないので、そこに到達できるといいですねえ。大きなビジネスに出来なくても、スマホとシームレスにつなぐことが出来たら、この後にもつながる。例えば、先のお話みたいにスマホで育てたキャラと体験型施設で遊べたり、プレイステーションVRに持っていっても面白くなる可能性が出てきます。そこまで行けばプラットフォームになれる。
ん、プラットフォーム? そうか、これ、ポストペット以外でも…。
八谷:「御社のキャラクターのデータをもらえれば、VR版を廉価で作りますし、カスタマイズもしますよ」ということですね。お気に入りのキャラクターを、普段はスマホでかわいがって、ショッピングモールに会いに行く。その際に、どういうリアクションがかわいいのか、何をすると嬉しいのか、ポストペットVRを開発することでどんどん経験値を積んでおければ、と考えています。
…例えば「だっこ」の動作に著作権とか取れるんでしょうか?
八谷:調べたことはありませんがアイデアなんで、著作権は無理じゃないでしょうか(笑)。何かを独占して知的所有権で大もうけ、というのではなくて、それぞれのキャラクターにマッチした世界観や動きをコンテンツとして、そのキャラクターを愛している人達を楽しませる、というのが、日本人である我々に合ったやり方だと思います。そういう「愛玩VRアプリ」を作る際の基礎みたいなのが自分たちで作れたらいいな、と。
日本はキャラ大国だし、アジアでも受けている。親和性が高そうです。ううむ、もっと欲張ってもいいくらいのプロジェクトではないですか? クラウドファンディングといわず、VCから出資を仰いで…
本当に命懸けなら、慎重になるのが当然
八谷:欲張ると大きな話になって、大きな話になると、当初計画を柔軟に変更したり、時間をかけることが難しくなってきますよね。それに、いろんな会社と組むことが難しくなるかもしれませんし。
人が増え、ステークホルダーが増えればそうなりそうですね。
八谷:新規事業だと「一刻も早く結果を」と言われることが多いですが、僕は、期間がかかることも悪いことばかりではない、と思うんです。「ユーザーと一緒に作る」のであれば、かけた時間は無駄にならない。M-02Jは「ナウシカのメーヴェで空を飛びたい」と思ってから、昨年の場内周回飛行までに13年かかりましたが、その間に小型ジェットエンジンやIT系のデバイスが、猛烈に安く、しかも高性能になりました。なにより自分も13年間すごく楽しみましたし。また、無理せず進めてきたから、僕も死なずに済んだのだと思います。
「命がけで」とか軽くいいますが、飛行機ですから、八谷さんは文字通り命がけのプロジェクトだったわけですよね。
八谷:ええ。自分が死ぬのもごめんだし、会社が倒産するのも避けたい。ならば、無理せず、どうすれば生き抜けるかを考える。すると、時には回り道をしたり、あるいはリスやクマみたいに状況が良くなるまで冬眠するのもありだな、となる。でも、関わる人やお金が多すぎると、それが許されなくなりそうですよね。「この人数分の売り上げを次の四半期で」みたいな話になっていくので。
外は吹雪なのに「死んでもいいからどんぐり拾ってこい!」と強制されるかもしれない。
八谷:規模があった方がやりやすいことも当然ありますが、小さいことのメリットも当然あります。それと経営者のキャパシティが…ペットワークスは取締役全員が「ぼくたちが管理できる組織って、10人以下だよね」と自覚してますから。
笑うところなのかどうか…。でも、そういう考え方は大企業の新規事業にも参考になるかもしれません。八谷さん流の「新規事業のコツ」を、最後にまとめていただけませんか。
八谷:参考になるかどうか分かりませんが、まず、やりたいことをやること、そして何より「人に見せること」が大事。その企画が世の中で受けるかどうかを早めに知ることができます。そして人に見せることを通して、好感を持って応援してもらえるように、「見せ方」を考えるようになるでしょう。その次に、お互いに楽しくやれそうな企業や個人を巻き込んでいく。自分たちだけで全部まかなう必要はなく、多くの人と組んでやったほうが、お祭りに近くなっていきますし。
予算がないならないなりに、そのプロジェクトに意義があり、楽しそうだったら人はついてくると信じて、小さな雪だるまを大きくしていきます。クラウドファンディングも、そのひとつの方法だと思います。そしてとれるリスクと取れないリスクを見極めつつ、ゆっくり着実に、ってところですかね。

登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。