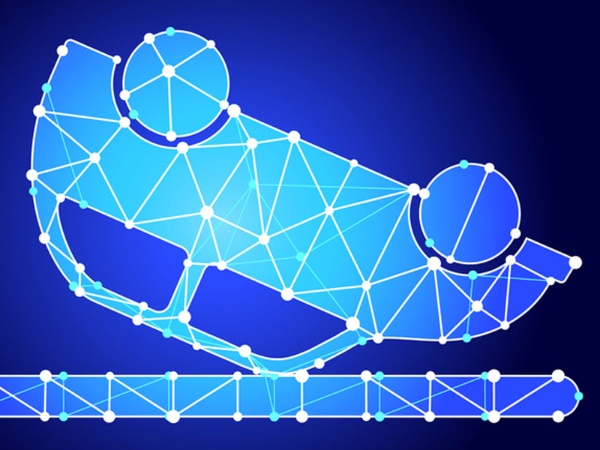米国のサンフランシスコには、肉だけではなく、シーフードも「植物」で作ってしまおうというスタートアップがある。グーグルのシェフも一目惚れしたという「植物エビ」を試してみた。さらに、ワインを醸造ではなく化学的に合成して再現するスタートアップも登場。何でもコピーする「フェイク(偽)フード」の潮流はどこへ行く?
「植物肉」の米ビヨンド・ミートや「植物卵」の米ハンプトン・クリークに触発されて、植物性タンパク質でシーフードを代替する「植物魚」を開発するスタートアップも登場した。海洋生物の多様性と保全を研究していたドミニク・バーンズ氏が、2015年に創業した米ニューウェーブ・フーズだ。CEO(最高経営責任者)を務めるバーンズ氏は、「今や世界の魚の消費量は牛肉を上回っていのに、そのサプラチェーンはサステナブル(持続可能)ではない」と警鐘を鳴らす。その課題を解決するソリューションとして、植物性タンパク質でシーフードを代替することを思いついた。

目を付けたのが、エビ。水産資源の中で市場規模が最大級であると同時に、乱獲や養殖による環境破壊が問題になっている。共同創業者の材料科学者と共に、エビが実際に食べている藻類やエンドウ豆の植物性タンパク質を使い、「植物エビ」を開発した。
創業して4カ月後には、米グーグル(サンフランシスコ拠点)の社員食堂のシェフの目に止まり、約90kgをサンプル出荷。シュリンプ・タコスやココナッツ・ロールとして振る舞われ好評を博したという。年内に約230kg/日の量産体制を整え、来年からグーグルなどの社食やレストラン向けに出荷したい考えだ。
サンフランシスコにあるニューウェーブ・フーズのオフィスで、試食の機会を得た。オフィスといっても、事務用品を取り扱う大型小売りチェーン「オフィスデポ」の2階フロアに用意された、複数のスタートアップが入居するインキュベーション施設の一角を間借りしている。
共有の打ち合わせスペースに用意されていたのは、エビフライとエビのソテーだ。油で揚げたり炒めたりすれば、多少は味をごまかせるからだろう。将来的には「シュリンプカクテル」として生で食べられる製品を開発することが目標だが、現時点ではそこまで開発が進んでいない。

エビ特有のプリプリ感があまりない…
早速、エビフライを口に運んでみると、若干違和感があった。エビのプリプリ感が、あまり感じられないからだ。本物のエビと比べると、しっとり感も乏しい。エビフライを食べ慣れた日本人記者の期待値が高いのかもしれないが、続いて食べたソテーも、おおむね同じような印象だった。
ただし、植物エビの断面を見ると、エビの筋肉繊維の構造を模倣しようとしていることは伝わってくる。エビの表面は藻類由来の赤い色素で模様を再現しており、エビの風味も感じられる。
そんな感想を伝えると、バーンズ氏はこう話してくれた。
「確かに、エビを噛んだときに感じる特有の弾力やしっとり感を再現するのは難しいのは事実です。牛肉や豚肉、鶏肉を植物性タンパク質で再現するのより、ずっと難しい。しかも、私たちは牛や豚、鶏を丸ごと食べることはありませんが、エビは丸ごと食べる数少ない生き物なので、カラダ全体を再現しなければなりません。逆に言えば、難しいからこそ挑戦する価値があります」
「アメリカ人はむしろ、シーフード特有のにおいに抵抗を感じる人も多い。植物エビなら、そうしたにおいをマイルドにできます。これまでも肉の代替製品はありましたが、シーフードはありませんでした。植物エビは、アレルギーの心配もなく、需要は大きいと確信しています」
創業間もないニューウェーブ・フーズにとって、本格的な製品化はこれからで、技術開発が進めばより本物に近づく可能性はある。バーンズ氏は、将来的には「植物エビ」だけではなく、「植物マグロ」や「植物サーモン」も実現したいと構想をふくらませている。
ワインを“コピー”する「合成ワイン」
既存の食品の分子構造を解析し、全く別の手法で再現してしまおうという動きはほかにもある。ワインだ。おいしいブドウを毎年育て、時間をかけて醸造するのではなく、ワインの「味」を実現している成分を化学的に合成しようというのだ。ブドウも使わず、醸造もしないために、量産が可能になれば低コストで、高級ワインと同じ味を実現できることになる。
そんなビジョンを掲げて研究を続けるのが、アヴァ・ワイナリーである。サンフランシスコの倉庫街にオフィスを構え、天井からはドクロの旗が掛かっている。何やら物騒な印象だが、どうやら「ワインパイレーツ(ワインの海賊)」という意味のようだ。業界に革命を起こそうという意気込みが伝わってくる。
オフィスを訪れると、テーブルに並んだ数十杯のワイングラスに入った赤い液体を、男性がテイスティングしていた。この液体が、ワインの分子構造を解析し、醸造ではなく化学的に再構成した「合成ワイン」である。それぞれワインの「レシピ」が異なり、ソムリエ資格を持つ社員が味をチェックしていた。

アヴァ・ワイナリーの創業は2015年。ワインが含有する数百種類の化合物を、製薬業界などで使われている解析装置で分析し、どの物質がワインの味に影響しているかを特定して、その成分をエタノールに合成する。つまり、既存のワインの成分を、化学的に「コピー」するのである。ワインが含む化合物のすべてを完全に再現するのではなく、あくまでも人間が感知できるものだけだ。共同創業者のアレック・リー氏は「それで十分」と話す。
合成にかかる時間は約1時間。長期間、醸造する必要がないために生産効率は高く、製造方法はコーラのような飲料に使用されているものでいいという。毎年、ブドウの出来具合に味が左右されることもなく、在庫が切れることもない。既存のワイン業界からは反発もあるが、一部のワイナリーからは熟成の管理などに技術を応用できないかといった関心も寄せられているという。
日本酒のコピーも可能
試飲したのは、合成した白ワイン。コピーの対象としたのは、デザートワインの一種でマスカットから作られるモスカートと呼ばれるワインだ。
グラスを傾け回してみると、液体がグラスをつたって落ちるのが早く、本物のワインと比べて少し粘性が弱いような印象を受けた。色も普通の白ワインよりも薄い。少し発砲している。鼻をグラスに近づけると、甘いマスカットのような香りがする。そして口に含んでみると、確かにワインのようだ。
ちなみに、記者はワイン素人である。当然、ソムリエ資格も持っていない。そのため、ワインをどのように表現して良いのか分からないが、近所のスーパーで買ってきて普段、家で飲むようなワインとしては、価格次第で「合成ワイン」は十分に消費者に受け入れられる可能性があると感じた。
このワインは競技会にも出品中だという。税制上、ワインに分類されるかどうかなど課題はあるが、リー氏は年内にも初出荷したいと意気込んでいる。
ちなみに、ワインの試飲の後、試作段階だという「合成日本酒」のコピーも出してくれた。これには正直、驚いた。ワインとは違った日本酒の特徴を再現していたからだ。つまり、成分の分析によって、極端に言えば何でもコピーできてしまうというわけだ。
有名ワインの成分をコピーすることについて、法的に問題ないのかと聞くと、「ワインに含まれる化合物は自然によって作られるもので、ワイナリーが化合物の知的所有権を持つわけではありません。ブランドやマーケティングをコピーしなければ問題ないでしょう」とリー氏は話す。また、既存のワイン業界からは、「ワインは複雑な組成でできており、完全にコピーできるわけではない」といった主張も出ているようだ。
こうした合成ワインを取り巻く周囲の反応を聞いていると、かつて音楽が、レコードがCDに、CDがMP3に進化した際に繰り返し聞かれた議論を思い出した。レコードがCDに進化したときには、「デジタルでは再現できないアナログの良さが失われる」、CDからMP3に進化したときには「音質がさらに劣化する」といった反発が、音楽業界や音楽ファンから巻き起こった。だが、結局は利便性向上とコスト低下をもたらすデジタル化を消費者は支持し、そうした反発は吹き飛んでしまった。
合成ワインや、これまで見てきた植物性タンパク質による肉や卵、魚の代替製品についても、同様の議論が今後、起きてくるかもしれない。保守的な食の分野では、新たな技術に対する不安は大きい。もちろん、安全を確保することは絶対に必要だ。そうした課題を克服できれば、デジタル化が起こした変革と同じような地殻変動が、食の分野でも起きる可能性はあるだろう。
登録会員記事(月150本程度)が閲覧できるほか、会員限定の機能・サービスを利用できます。
※こちらのページで日経ビジネス電子版の「有料会員」と「登録会員(無料)」の違いも紹介しています。