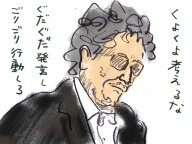「3Dテレビ元年」ということが喧伝されはじめる直前まで、2010年が「電子出版元年」と言われていたことをおぼえておいでだろうか。
結果は、いずれも空振り。モノ離れ元年。特に電子出版元年の方は、iPad(アイパッド)の需要が一巡すると完全に忘れられた。
なぜだろう。
電子出版元年報道が羊頭狗肉かつ竜頭蛇尾の様相で推移してきた理由は、おそらく、家電業界が電子情報端末の需要に期待している以上に、既存メディアが電子出版の未来に不安をおぼえたからだ。新聞雑誌およびテレビの皆さんは、活字情報が電子化されることに、本能的な反発を感じているのだ。いや、反発というよりも、より端的に恐怖かもしれない。木の洞から出た尺取り虫がはじめて鳥を見た時の感じ。
「ん? あいつらの口元はなんだかやけに不吉なカタチをしているぞ」
と、ニュースが入ってきた。
「電子書籍の市場拡大を前に、国内の主要459出版社が加盟する日本書籍出版協会(書協)が書籍の電子化に際して著作者と結ぶ契約書の「ひな型」を加盟各社に向けて作った」(10月6日 asahi.com)というお話だ。
以下、記事(の一部)を引用する。
《「ひな型」では、出版社は、(1)DVD-ROM、メモリカードなど電子出版媒体に記録した出版として複製し、販売できる(2)インターネットなどを利用し、公衆に送信することができ、ダウンロード配信やホームページに掲載して閲覧に供することができる(3)データベースに格納し、検索・閲覧に供することができる、などとしており、一方で、出版社側の役割りとしては「価格、広告・宣伝方法、配信方法および利用条件などを決定し、その費用を負担する」とある。》(10月6日 asahi.com)
記事は続けて、この「ひな型」が出版社側に有利で、それゆえ、著作者たちの反発が予想されるとした上で、一方、「ひな型」は、叩き台に過ぎず、加盟各社を縛るものではない旨も併記している。
煮え切らない記事だ。
あるいは、煮え切らないのは記事ではなく取材先の方で、記者は、単に煮え切らない状況を描写しているだけなのかもしれない。
問題はもっと手前の部分にある。すなわち、この先、著作者と出版社は、どうやって本を作っていくのかというところに、だ。
私自身の現時点での見通しは、ちょっと悲観的だ。
はじめて底引き網の網の目から向こう側を覗いた時のヒラメみたいな気持ちと言ったらご理解いただけるだろうか。
「うーん、この不思議な壁の先にはとても厄介な未来が待っている感じがするぞ」
と、ヒラメは思っている。が、実際のところ、彼の未来は壁の向こう側にではなくて、手前に限定されている。二度と網の向こう側に戻ることはできない。
流通形態と、読書習慣と、制作過程。
それぞれに深刻な網の目がかぶさって来るはずだ。
しかも、一度はじまった変化は、二度と昔には戻らない。
街からCDショップが無くなり、写真屋が根絶やしになりつつあるのと同じように、この先、書店が少しずつ消えていく中で、本を読むわれわれの読み方も以前と同じではいられない。本を書く人間の書き方も変わっていく。
で、気がついた時には、あらゆる文字がGoogleの資産になっている――のだろうか。
私は過剰反応をしているのかもしれない。
経験したことのない事態に直面すると、無知な人間は闇雲な不安を抱く。
こんなことではいけない。
もっと心を広く、柔軟な姿勢で時代の変化に立ち向かうべきなのかもしれない。
そう。網はフランス語で友達。運命だ。どおんと受け入れようではないか。
泳げる範囲は狭まるかもしれない。でも、この先、網が導いてくれる世界には、泳いで寝そべって食べて死ぬだけだったこれまでの平凡なヒラメの一生とは違う、新しい未来が待っているかもしれないではないか。
たとえば、高級魚として一流の料亭のまな板に乗ることは、地味な底魚として水面を見上げて過ごす境涯に比べれば、ずっと晴れがましい生き方であるのかもしれない。
まな板の上のヒラメは……潔くない。上目遣いに板前を見る。ちょっと恨みっぽい。うん。私は不安だ。とても。
まず流通について。
ここが最も大きく変わるポイントだ。
何より、これまで紙に印刷されていた文字が画面の上の信号に変わってしまう。この違いはとても大きい。読み方も、売り方も、書棚に並べる蓄積の仕方も、すべてが変わってくる。
とはいえ、文字は文字だ。
紙の上のインクであれ、画面上の光の明滅であれ、伝えているところのものは、データであり情報であり文章だ。本質は媒体にではなく文字そのもののうちにある。文章。ひいては人間の営為に。
そう思えば、文字が紙という「ブツ」を介さずに提供されることは、悪いことばかりではない。
何より地球にやさしい。
紙の使用量が減ることは、そのまま森林の保護に直結している。
書籍という物理的な存在を運んだり積んだり並べたり断裁したり焼いたりすることから生じる環境負荷もゼロにできる。
そう考えれば、データを電子化することは、良いことずくめだ。流通、保管、検索、変換。あらゆることが完全に重さやカビや虫食いから自由になる。素晴らしいじゃないか。
が、問題は環境負荷とは別のところにある。
媒体が変われば流通が変わるのは当然だが、変化はその部分だけでは済まない。
媒体を取り巻く環境や、独占の様相や著者と業者の関係も、流通の変化を受けて変わらざるを得ない。
最初のうち、電子書籍は、DVDやUSBメモリーに焼いた形で売られ、あるいはダウンロード販売されることになる。
一部の人々が心配している通り、不正コピーが出回ることもあるだろうし、アンダーグラウンドな市場だって形成されるだろう。
でも、書籍がデータとして販売されている実態がある限り、本が本である形式は守られる。書籍が、ひとまとまりの文字の集合体として、ひとまとまりで扱われている限りにおいて、紙が介在しようが介在しまいが本は本だ。
紙の上に印刷した本は、不自由なものだ。検索もできないし、一括処理もできない。インデックスも作れない。
が、その不自由な紙の書籍は、一方において堅固でもある。バラすこともできないし、勝手にページを組み替えることもできない。きちんと一ページ目から、著者が意図した順序で読むほかに読み下す方法がないわけだから。
【お申し込み初月無料】有料会員なら…
- 専門記者によるオリジナルコンテンツが読み放題
- 著名経営者や有識者による動画、ウェビナーが見放題
- 日経ビジネス最新号13年分のバックナンバーが読み放題