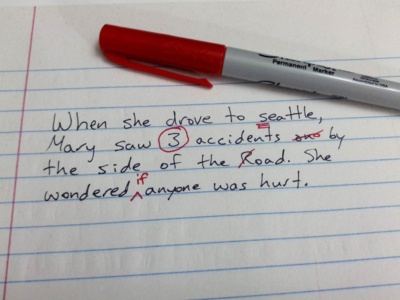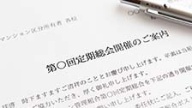日経ビジネス6月18日号の特集「早期退職の経済学」の取材では、定年を迎えることなく職場を離れた人たちに会って話を聞いた。取材期間1カ月ほどのうちに、過去に人員整理に踏み切った大企業でずいぶんたくさんの社員に、去っていった先輩や元上司らの動向をたずねてみたが、誰1人として答えられなかった。薄情とは思わない。会社側がそこまで把握する義務はない。田舎へ帰った人や、元の職場とは連絡を絶ちたいという退職者もいるだろう。
だからこそ、本特集をやる意味があったと思う。先輩の“その後”が見えにくいからこそ、現役社員は「40~50代で会社を辞めてしまうって、どんなものなんだろう」という疑問を抱きやすい。特集ではシミュレーションや個人の体験談、識者のコメントを紹介しつつ、十分に早期退職に関する判断材料を提供した。だが、たくさんの退職経験者に会えば会うほど、「退職後の生活は千差万別である。退職という決断が正しかったかどうかの判断すら難しいものだ」と感じるようになった。そこで、誌面の都合上、特集には盛り込めなかったものの、特に印象に残った3人の退職体験談を紹介したい。早期退職について考えるヒントとして、特集と併せてお読みいただければ幸いである。
まずは退職後に冒険的で、興味深い進路を選択した、吉田矢裕嗣さん(57歳)である。大学卒業後、大手百貨店に就職、長年アパレル部門のバイヤーとして勤務した。2009年秋に早期退職に応募。「経営統合によって業務の効率化がどんどん進み、自分のやりがいと会社の方向性に溝ができてきた」というのが、直接的な理由だ。定年まであと5年もあるし、その気になれば会社は65歳まで働く場所を用意してくれただろう。だが、思い切って退社。そして、翌春に妻と長男を連れて種子島へ移住した。
それまで屋久島や沖縄には度々訪れていたものの、種子島には縁もゆかりもなかった。会社が早期退職を募る直前に、あるアパレルメーカーのイベントで種子島の写真と出会い、島に関心を抱く。ロケットの打ち上げ基地の存在や、気候の良さを知るにつれて、漠然と移住へと気持ちが傾いていった。結果的に島へ渡るために早期退職を決断したとも、希望退職というきっかけが島行きを後押ししたともいえる。
生まれ育ちは東京都練馬区。老いた母は今も豊島園に住んでいる。妻と小学2年生の長男は反対しなかったが、母親は強く反対。ずっと賃貸住まいだったので、家のローンはなし。息子の年度末までに引越しの準備を整えて、種子島へ渡ってから職は探し始めた。
おカネのシミュレーションはやってみたが、「あくまで家族を説得するための資料作りに過ぎなかった」と笑う。吉田矢さんの決意は固かったからだ。バイヤー時代に上司を説得するためにやったようなことと同じ。バイヤーとしての信条は「現場現物を見なければ判断できない」。もちろん、何の準備もしなかったわけではない。再就職支援会社のパソナキャリアの「セカンドライフ支援プログラム」を受講。「田舎暮らし支援コース」で就農やNPOの活動のあり方を学んだ。パソナキャリアカンパニーのプレジデントである渡辺尚氏は「多くの企業が早期退職を実施するので、大手企業の部課長経験者が大量に転職市場へ流れ込んでいる。今の50~60代は若くて元気。中小企業や地方の会社にとっては採用の好機だ」と指摘する。吉田矢さんのようなキャリアの持ち主は、地方では確かに稀少。待遇さえこだわらなければその経験を求める職場は多いだろう。
見込み違いだったのは、離島の物価。ガソリンや食品、消費財は、物流費がかさむために割高なことだ。家賃こそ東京と比べて格安だったが、生活コストは高かった。また、島では過疎化が進んでいる。息子は「複式授業」と呼ばれる、2学年の生徒が1つの教室で学ぶ方式で勉強している。同級生の男の子は1人だけ。だから、小学校の生徒たちとJAXA職員が触れ合うイベントを企画したりと、いろいろ考えている。最初はバイヤーとしての独立・起業を狙っていたが、今は地元の物産を商工会議所のような組織で企画・販売する仕事に就く。1年契約の職員だが、周囲に必要とされて働くのは幸せだと感じている。
取材の最後に「種子島への移住は成功だったのですか」と聞いてみた。吉田矢さんは少しだけ思案して「石の上にも3年というから、2年しか経っていない今はまだ分からない。ただ、行動に移して良かったとは思っている」と語ってくれた。古巣の百貨店には感謝している。都会で磨いたバイヤーとしての腕が、島での暮らしや仕事に役立っているのだという。
56歳からのベンチャー経営
横浜市内でお会いした仲里一郎さん(60歳)は、退職後にベンチャー企業を立ち上げている。新卒で市内の建設会社に就職してから33年働いたが、2008年7月に56歳で職場を去った。ただし、いわゆる「早期優遇退職」ではない。自己都合による退職だ。2009年2月に野菜の卸・販売の大喜コーポレーションを設立。「地元産の安心・安全な食材を『物語』とともに売りたい」と熱く語る。
定年前に会社を辞めたきっかけは、50歳を過ぎてからのプロジェクト推進部長就任にさかのぼる。建設業でも単に「箱物」を作るだけではノルマばかりに追われ、閉塞感で社内がいっぱいになってしまう。請け負うだけでなく地域に合った土地の活用法を提案していくような商売ができないか。そんな新規事業の責任者を任された。
そこで食物工場の運営から野菜販売まで手がける農業法人を社外の企業と立ち上げることになった。仲里さんは販路開発の責任者として、その共同出資会社へ出向。3年経って古巣の建設会社に戻ることになった際、漠然と「独立しよう」という気持ちになったという。「新規事業が軌道に乗らなかったから、けじめをつけたかった」と殊勝に語るが、仲里さんの母親が還暦を過ぎてから事業を起こしたことも影響している。ちなみに母親は80歳を過ぎた今も現役の経営者だ。妻も賛成してくれたうえに、家のローンなどを抱えているわけでもないから退職を迷うことはなかった。
「チャンスの神様には後ろ髪はない。見つけたら、すぐに前髪をつかめ」と聞いたことがある。仲里さんは「自分は間違いなくつかめた」と笑う。会社を設立した翌年の2010年8月に植物栽培用LED(発光ダイオード)照明を開発しているベンチャー企業、キーストーンテクノロジーの社長と知り合う。レストランの軒先で野菜を売る仲里さんに興味を持って声をかけてきた。仲里さんの野菜への思いを知った同社社長は、自社製品の販売を仲里さんと共同で行うことにする。仲里さんはそこに古巣の建設会社までも巻き込んで、販売代理店を設立してその会社の取締役にも就いている。
現在の収入は「女房と2人で暮らすにはトントン」という。「借金はしていないし、生活レベルも落とさなかった。将来への(事業の)種まきはこの4年で済んだ。今年は収穫の年になる」と語る。
今回取材した退職経験者のうち唯一の公務員がAさんである。57歳まで公立高校で物理教師を務めてきた。妻の病死をきっかけに体調を崩した。何とか1年は頑張ったものの、2010年3月に定年を前に退職。非常勤講師として再雇用されたので、そのまま同じ高校で週に3日働いている。ただし、学年主任という管理職の業務からは退職で解放された。妻の死が直接のきっかけではあるものの、もともと喘息持ちで自分の体調に不安があったため、50歳ぐらいから早めの退職は「夢物語程度」に考えていたそうだ。
退職前に公務員向けのセミナーに参加、年金や生活費などのシミュレーション方法を学んだ。もともと妻を亡くしてからはエクセルを使って家計簿をつけていた。そこに退職金と生活費、税金、保険など様々な要素を加味した。「年金の受給まで、何とかなりそうだ」と判断して退職を決意した。高校1年生の長男のために毎日、弁当や夕飯を作らなければならない。フルタイムの勤務はきついという事情もあった。
早期退職後も働き続けたのは、お金の心配もあるが、「世間から離れてしまうのはまずい」という恐怖感もあった。「教師は立ちっぱなしの肉体労働。校長や教頭にならない限り、50代後半だと自分には体力に辛かった」と話す。自宅で学習塾を開けば家事と両立できそうだと考えたこともあったが、夜型の生活になれば長男に夕飯を用意できない。学習塾案はすぐにあきらめた。
【お申し込み初月無料】有料会員なら…
- 専門記者によるオリジナルコンテンツが読み放題
- 著名経営者や有識者による動画、ウェビナーが見放題
- 日経ビジネス最新号13年分のバックナンバーが読み放題